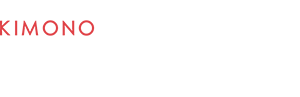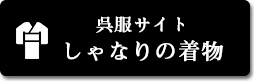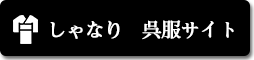着物の雑学①
着物の部位が使われる言葉
襟を正す
漢の宋忠(そうちゅう:後漢時代末期の学者、政治家)と賈誼(かぎ:前漢時代の政治思想家、文章家)が司馬李主に会った時、「纓を猟り襟を正して危坐す(冠の紐を整え、襟をきちんと直し、正しく座り直した)」という故事に基づき、衣服の乱れを正し、姿勢を正しくすることを意味するようになりました。そこから派生し、真面目な気持ちで物事に対処する態度を示すことを表します。
襟に付く
裕福な人は重ね着をして襟が厚かったことから、かつては襟元の様子で貧富が分かったといわれています。襟に付くとは、金持ちや権力のある人に媚びへつらう、追従するという意味で使われるようになりました。襟元に付くともいいます。
襟付きが厚い
平安時代、女性貴族の正装は幾重にも重ねた十二単でした。また、近世になると裕福な女性は小袖三枚襲(かさね)を定番としていたため、襟が厚く見えたことから、「襟付きが厚い」とはお金持ちであることを指します。逆に「襟付きが薄い」はみすぼらしいことを意味します。このように、襟元の厚さによって貧富の判断をしたのです。ひらひらレースのエリザベスカラーなど、日本だけではなく外国でもお金持ちの人々は布を贅沢に使うことを好んでいました。
領袖(りょうしゅう)
領は襟のことをいいます。つまり、領袖とは襟と袖。襟と袖は着物の中で最も目立つ部分であり、肝心なところという意味で使います。そこから派生して、主要人物または幹部など、人の上に立つ者を指したり、もしくは両腕であることの例えに使うなど、集団の中心人物のことをいいます。例えば、「派閥の領袖」などの使い方をします。中国晋時代の歴史書『「晋書」魏舒伝』にその記述があります。
袖にする
「身」が本体であるのに対し、「袖」は付属物。そのため、「袖にする」とは、ないがしろにすること。また、きものの袖に手を入れたままで何もしないことを意味しました。そこから、親しい人や思いを寄せてくれている人を邪険に扱い、全く試みないことを「袖にする」といいます。特に男女の関係において、付き合いを一方的に断り、相手に冷たくつれない態度をとる場合に使われます。
袖の下に回る子は打たれぬ
叱ろうと思った時に、逃げて回るような子なら追いかけてでも打ちたくなるが、自分をしたってすがりついてくる子はかわいく思えて打ちたくても打つ気になれないこと。袖の下に回る子は可愛い・怒れる拳笑顔に当たらず・尾を振る犬は叩かれずなどと同義で、従順な人は誰からもひどい仕打ちを受けることはないことの例え。
袖に墨付く
人に恋い慕われるときは、衣の袖に墨が付くという言い伝えがありました。そのことから、「袖に墨付く」とは誰かに恋い慕われたしるし、または前兆であることをいいます。
袖を引く
袖を取って人を誘ったり催促、注意を与えるという意味で使います。ただ、強引にぐいぐい引っ張るのではなく、奥ゆかしく周りの人に気づかれないようにこっそりとするのが「袖を引く」状態です。恥ずかしさや照れをこめながらも気品をもって行います。例えば、早く帰ろうと相手を誘う場合、そっと注意をする場合に使います。
袖から火事
明暦3(1657)年、1月18日、19日にわたって江戸の大半を焼き尽くした明暦の大火。本郷円山本妙寺で施餓鬼(せがき:仏教における法会)の仏事で焼いた振袖が強風にあおられ、空に舞い上がったことが原因で大火事になったと伝えられています。そのため、「袖から火事」は、小さなことがきっかけで大きなことが起こることのたとえで使われます。
袖を連ねる
何人かの人が連れ立って行くこと、また進退を共にすることをいいます。
「袖を連ねて来場する」「袖を連ねて辞職する」などと使い、「袂を連ねる」という言葉も同じような意味で使われます。
ない袖は振れぬ
江戸時代、「袖を振る」ことは求愛のサインでした。相手に袖を振って見せ、袖を振り返してもらえると、それはOKのしるし。未婚女性が振袖を着たのは、袖を振るためだったのです。
ない袖は振れぬというのは、振りたくても袖がなければどうしようもないということで、いい返事をしたくても先立つもの(袖)がなければその気があっても無理(振れない)ということでした。そこから転じて、お金を貸したくても財力がなければ貸せないということを意味するようになりました。
小袖料
昔は、結納として、金銭ではなくきものの小袖を贈っていました。そのため、結納金のことを「小袖料」というようになりました。主に関西で使われるのが「小袖料」ですが、京都では「帯地料」、関東では「御帯料」ということが多くなっています。なお、小袖の返礼には袴を贈っていたため、結納返しとして包むお金は「袴料」と呼ばれます。
衽(おくみ)
「壬」という漢字は「中に入れ込む」という意味を含み、衣へんに壬と書く「衽」は、内側に入れ込む部分ということになります。着物の前身頃に衽が付属したことで、紐一本で前合わせができる衣服となりました。おくび、おおくび、上交(うわがい)ともいい、おはしょりの衽線と裾の衽線が一直線になるように着付けをします。
振り
女性の和服の袖の、袖付け止まりから袖下までの縫い合わせていない部分のこと。「人の振り見て我が振り直せ」というのは、着物と襦袢の振りの丈が合っているか、他人の振りを見て気づかされるということが語源であるといわれています。 また、「振り」には動作の仕方や様子、姿・容姿という意味もあります。
袂を分かつ(たもとをわかつ)
袂とはきものの袖の下にある袋状の部分。昔から、袂には魂が宿ると信じられており、好きな相手に対して袖を振ることで相手の魂を呼び込めるとされていました。そして、結婚をすると袖を振る必要がなく、振袖の袖を短く仕立て直して留袖にしたということから、結婚により親と別れることを袂を分かつというようになりました。そこから転じて、考え方や価値観の違いから今まで一緒に行動を共にしてきた人と別れることを指すようになりました。
袂落とし
タバコ入れ・汗ふきなどをはさむ小さい袋のこと。紐の両端にその二個を結びつけ、懐中から左右のたもとに落として袂を落ち着かせました。男性は乗馬の時に袖が風でまくれないよう、女性は護身にも使いました。
袂に縋(すが)る
去ろうとする人の袂をとらえて引き留めること。重ねて懇願したり、相手の同情を引いて助けを求めたりすることも意味します。
裾捌き(すそさばき)
着物の足に当たる部分の縁を「裾(すそ)」といいますが、その長い裾が乱れないように上手に足運びをすることを「裾捌き」といいました。そこから転じて「捌く」は、複雑な物事を適切に処理することを意味するようになりました。また、「袱紗(ふくさ)捌き」は茶道の作法のひとつで、道具を拭き清める袱紗の扱い方のことです。
裾を肩に結ぶ
着物の裾を肩のあたりまではしょって結びあげた、きびきびとした姿。そのようなてきぱきとした格好で熱心に働く様子をいいます。また、苦労もいとわずに働くことを意味するようになりました。紐を斜めに交差してかける「たすきがけ」も似たような意味で使われます。
裾もの
裾(すそ)は、衣服の下端の部分から転じて、主要ではない末端の部分を表します。地面に近い部分であり「つまらないもの」という意味があります。すなわち、「裾もの」とは、取引用語で、質の良くない品物や下等品のことを指していうようになりました。
お裾(すそ)分け
衣服の下の縁の足にあたる部分を裾と呼びます。地面に近い末端の部分であることから、「つまらないもの」という意味があります。お裾分けは他人からもらった品物などの一部をさらに知人に分け与えることで、目上の人に対して使うことは適切ではありません。また、山のふもとは山裾、ランクの低い品物を裾物といいました。きものを着たとき、長い裾が乱れないように足を運ぶことを「裾さばき」といいます。
気褄(きづま)を合わす
褄(つま)とは、きものの裾の左右両端の部分のこと。着る時は、下前の褄を上げて位置を決めます。この動作を適当にしてしまうと、中心線や裾がきれいに出ないため、美しく着るために褄を合わせることは大切です。気褄とは、人の機嫌のことをいい、「気褄を合わす」とは、相手が気に入るように調子を合わせる、機嫌をとることを意味します。
褄を取る
着物の裾の両端の部分を「褄(つま)」または「褄先」と呼びます。裾の長い着物の褄を手で持ち上げて歩くことを「褄を取る」といい、芸者は左側の褄を取って歩くことから芸者のことを「左褄」とも呼びます。
着物は通常、左が上になるように纏い、合わせが右側に来て右側が開きますが、左を上にして持つと裾から手が入りにくく、“芸を売っても身は売らない”という芸者の心意気の表れとなっています。
帯は感情を表現する
帯は“後ろの顔”ともいわれ、きもの姿に重要な役割を果たします。うれしいとか悲しいとか、感情を表現することもあり、「むしろを着ていても帯は錦」といわれるほど帯の合わせ方次第で、きものが決まるのです。これだけ重要な役割を果たす帯ですが、帯にまつわる言葉は意外と少ないです。代表的なことわざとして、「帯に短し、たすきに長し」…帯には短くて使えないし、たすきにするには長くて邪魔になる。物事が中途半端で結局何の役にも立たないことのたとえとして使われます。
帯祝い(腹帯)
古事記(712年)に神功皇后が懐妊した際、巻いたことが書かれており、それが起源になったという説もあります。お腹の子どもが順調に育ち、比較的安定した妊娠5カ月目の戌の日に安産を祈願してお祝いします。帯を巻くことで、お腹を保護し、胎児の位置を安定させるとともに大きくなったお腹による腰の負担をおさえる効果もあります。
戌の日に行うのは、犬が子だくさんで安産であるからといわれていますが、地域によって風習が違うこともあります。
帯解き
紐落しともいい、それまで付け紐で着ていたきものをやめて、帯で締めるようにする習わしで七歳のお祝い。(七五三まいりの源)このような習慣は公家や武家の間で行われていたものでしたが、江戸時代に町民の間にも広がりました。七五三まいりが11月15日になったのは、五代将軍綱吉の子徳松がこの日にお祝いをしたという説、旧暦にある「鬼宿」といわれる最吉日であるためという説があります。なお、三歳のお祝いは髪置き(生後剃っていた髪の毛をこの日から剃らずに残す)、五歳は袴着(初めて袴を着ける)といいます。 幸田美智子『衣のことば』より
兵児帯(へこおび)
鹿児島地方で、15歳以上25歳以下の青年のことを「兵児(へこ)」といいました。その兵児が普段に締めていたことから兵児帯といわれるようになりましたが、明治維新とともに鹿児島の風習が東京にも伝わり、広く用いられるようになりました。幅約50㎝~74㎝の縮緬地などをしごいて締めるものです。もともとは男物の帯でしたが、子どもが浴衣を着る時にも用いられるようになり、現在は女性が浴衣に締めることもあります。簡単に結べますが、ほどけやすいため、よそ行きには不向きです。
お太鼓
江戸時代の末期、東京の亀戸天神に太鼓橋という橋ができ、開通を華やかに祝うため、深川の芸者さんたちが招待されました。その際、芸者さんたちが橋の形を真似て帯を結び、その結び方が「お太鼓結び」と呼ばれて流行したといわれています。補助紐を使った、それまでにはなかった斬新な結び方で、あっという間に広がったのです。
はしょる
「端折る(はしおる)」が変化した語で、もとはきものの褄や裾を折り上げて帯などに挟むことをいいました。このように、きものの端を折って短く縮めることから、省略することを「はしょる」というようになったのです。今でも、女性がきものを着る時に着丈より余った部分を腰で折り返してできる部分を「おはしょり」と呼びます。「はしょる」は「おはしょりにする」ともいいます。
繰越し
くりこしとは、女性が和服の衿を抜いた(繰った)ように着るため、衿肩あきを肩山より後ろ身頃側へずらすこと、またはそのサイズのことをいいます。一般的にそのサイズは、5分(約2㎝)とされていますが、振袖などの礼装きものは多めにするなど、好みで決めます。会計などでは、次期の会計に組み入れることをいいます。
襦袢(じゅばん)
きものを着る際の肌着。襦も袢も下着を意味する言葉です。この「じゅばん」という音は、アラビアの男性が着る「ジュッパ」が元になっています。ここから派生して、フランス語でペチコートを表す「ジュポン」という言葉、それがさらにズボンともなりました。すなわち、ズボンと襦袢は語源が同じということになります。